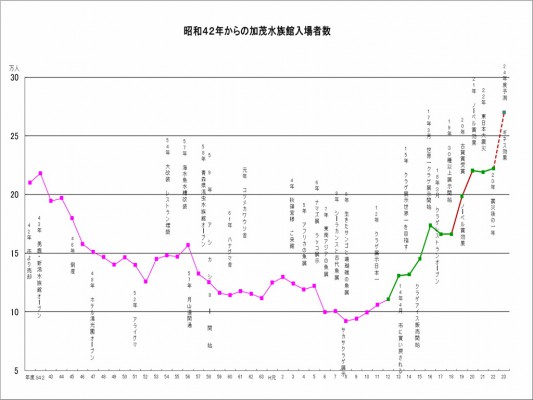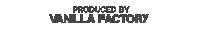独立学園は山奥の狭い谷間に建っていたものだから、遠くまで見通せていい眺めなのはサルッパナと呼んだ山の方角だけだった。
右も左も皆山に囲まれて人家も見えず、人の手が入ったことのない原生林が山並になって綺麗だったが、本当に狭い所にへばりつくようにして学園村は存在していた。
朝に夕に眺めたあのサルッパナの後ろ側はどんな山なのか、学園生だけではなく地元のひとさえ知っているのは、わずかしか居ないのではないかと思う。
私は真冬の厳寒期に三度、尾根を越し、陰のブナの原生林で兎追いをした事がある。今回はその時の事を書いてみようと思う。
サルッパナの向こうの原生林を、親父さんは「ナベコ」と呼んでいた。行ってみると分かるのだが、広い原生林で、果てしなく続き一歩踏み込むとどこも同じに見えて、方角さえ判らなくなる程の見事なブナ林だった。
親父さんはその大きさを、「ナベコ一千町歩」と表現していた。紙切れの手紙が届いて誘われて、初めて行ったのは二年生の時の事だと思う。
行く度に疲れ果てて、死ぬ思いをして帰って来るのでもう絶対に山には行きたくないと思うのだが、一週間も過ぎると又山に行きたくなるから不思議だ。
行くと決めた丁度その日は、「満月の月回り」で夜になればバンドリ撃ちができる条件だった。親父さんは「ナベコにはだれもバンドリ撃ちに入っていない。ものすごい数のバンドリが居る。せっかく行くのだから夜まで粘ってバンドリも撃とう」と言った。
何が幸いするか分からないもので、バンドリ撃ちが出来る月回りが、全員の命を助けたと言えると思う。なぜ助かったのかこの辺は後で述べるので次第に分かってくると思う。
参加したのは私の他に地元の三年生一人と寮生が二人居た。鉄砲は親父さんのが一丁と、近所の人から借りた「24番の村田銃」が一丁で、三人が追い役をする段取りだった。
朝の5時ごろだったろうか真暗いうちに起き出し囲炉裏の側に来ると、いち早く親父さんの奥さんが起きて働いていて、子供の頭程もある大きな握り飯をこしらえてくれた。
私と二人の学園生は、親父さんの家に泊まっていたので、奥さんは四人分のおにぎりを作ってくれた。皆張り切っていて、親父さんもナベコに行くという事で、いつもとは全然違い特別力が入っていた。
「明日は夜まで山に居て、暗くなったらバンドリ撃ちをするぞ!!」と、前の日から全員に号令を掛けていた。従って、お握りは二食分を持参することになった。
風呂敷に握り飯を二つ包み、腰に巻いてしばり付け暗い中を出発した。小倉林道の入口を過ぎ、「アカハゲ」と呼んだ次の沢の辺りから右の崖の上に上がって進む。雪崩で川沿いの車道は歩けないからだ。
サルッパナの頂上から尾根を半分ぐらい下がった辺りの中腹に、「クルミ平」と呼ばれる一寸広い台地が見える。その下に取り付いて登ってゆく、台地を越して尾根に近づいたあたりからブナの大木が繁り原生林となっていた。
そのまま真っ直ぐ尾根に登って裏側に越してゆく。ブナの林に入ると太い木の下は雪の上に、ムササビが食い散らかした10cm程の小枝が無数に散乱していて、誰も行かない山奥にはムササビが多いことが良く分かった。矢張り親父さんの言うとおりだった。
サルッパナというのは遠目に見たように、尾根は右にゆるく下がりながら向こうとこちらに馬の背状に急な勾配になっていた。
そして、裏側には尾根に平行して沢が一本流れていた。雪は沢を埋めていたが、所々で口を開けていて黒い岩肌が出ていて、切り立った両岸がいかにも危なそうに見えていた。
かなり大きな滝も有り、以前親父さんの近所の人が落ちて亡くなった事があると、滝を見下ろしながらその時のことをリアルに語ってくれた。「滝に落ちた人を引き上げて、あそこの木の根元に座らせて、助けを呼びに戻ったんだ。」「しかし間に会わず戻った時には亡くなっていた・・・」と、今でも雪に口を開けた滝が、妙に気味悪く目に残っている。
親父さんが段取りし、撃ち手が先回りし沢沿いの斜面を追い始めた。声を出して追っていると今逃げたばかりの兎の足跡があちらこちらにあり、山奥には随分兎が多く、感心させられた。
しかしさっぱり鉄砲の音がしない。どうも撃ち手と撃ち手の間を抜けられている様だった。苦労して追った結果は一匹のみだった。
親父さんが「ここに来る」と思った所には来ないで、撃ち手から見えない所を兎は抜けていた。前にも書いたが弱い兎はバカな生き物ではない、何かを察知して安全なところを走り抜けたのだ。
慣れた打ち手がもう二人も居たらこんな事にはならなかっただろう。同じ所を4~5匹も抜けたと、皆残念がった覚えがある。
鉄砲撃ちも大概こんなもので、生き物を相手にしているので、一ヶ所で大猟したという事はそうめったに無いものだった。
次の巻きに移動中、先を歩いていた親父さんが「ワスだ、ワスだ!!」と言っているので、「鳥のワシ」を訛って呼んだのかと思って見回したが何も飛んでいない。
さて何だろうと思ってよく見ると、少し向こうの急斜面が雪煙を立てて音もなく流れて木々を押し倒して、更にはるか下の方に流れて行った。
山の尾根には風で張り出した雪庇が出来る。高さ2mも3mもあって何かの拍子に崩れると、斜面のやわらかな雪を押し流すきっかけになる。
「表層ナダレ」を初めて見た。雪が水の様に滑らかに早く流れ下っていった。「ワス」は表層ナダレの事だった。音もしないしスピードも力もある。あれに襲われたら逃げられないと思った物だ。
それと怖いと思ったのは雪のスキ間で、急斜面に積もった4~5メートルの雪が、大きなナイフで切った様に50~60センチ、口を開けている。
降った雪が開いた口を覆うので落ちる迄気付かない。落ちてしまうと狭く身動きもままならず、手掛かりもなくなかなか上手に上がる事が出来なかった。
親父さんに「雪の割れ目に落ちて死んだ人も居る」と言われ、本当に怖かったものだ。
気を付けて歩いたが、2~3度落ちてしまった。広い原生林に追い手が間隔を開けて散ると遠くに声がかすかに聞こえるだけで、助けを呼ぶ声は届かない。カンジキをはいた足でやたらと雪を蹴って必死になってはい上がったものだ。
何回か追ったが兎は思いほか捕れなかった。その日は4匹で終わった様に思う。朝の意気込みはもう10匹も多く捕れて当然なほどだったが、親父さんの外は皆あの地を知らず、素人ばかりでは仕方無いかもしれない。
新雪をラッセルしながらウサギを追うのは疲れるし何よりも腹が減る。お昼に食べるはずのお握りは、十時頃に早々と食べてしまった。
昼前から猛吹雪になって、寒さで引き金を引けない程になっていた。そして腹が減って昼過ぎに二つ目のお握りを食べてしまった。
何時頃だったか定かでないが3時ごろだったろうか、皆疲れていたのでバンドリ撃ちはやめて帰る事になった。その頃はまだサルッパナの向こうの沢の近くだった。
こちら側と同じ様な長い急斜面を尾根まで登らなければ帰る事が出来ない。親父さんの指図に従って、ひどい吹雪の中を登り始めた。
足を大きく上げて目の前の雪を踏むと、ズブーと抜かりわずかしか登ることが出来ない。替わるがわる先頭になって登ったが、とっくに越せるはずの尾根にはなかなか出なかった。
私は完全にグロッキーになって先に立ってラッセルする力は失せていた。寒さと疲れ、それに何より空腹だった。このままここに座り込んで眠ったら、どんなに楽で気持ち良いだろうなと思った。
こんなに苦労するくらいなら、背負っている鉄砲で自殺した方がましだとも思った。そんな中で何とか頑張っていたのは、地元の生徒と親父さんだった。
夕方になり始め、薄暗さと、吹雪で見通しが悪く、どの辺に居るのかさっぱり分からない。
そのうち先頭にいた親父さんが「行く所がないぞ!」と言っている声が聞こえてきた。驚いたことにそこはサルッパナの頂上だった。周りは全て下りでもう登る所がない。
頂上には国土地理院が測量のために建てた、木の枝を組み合わせた高さ3~4mの三角点が有った。下の方に「河原角(かわらつの)の集落」の灯りが見えていた「アー助かった」と思った。
吹雪で地形が分からず慣れた親父さんもコースを間違えたのだった。頂上からは下るだけなので、急に元気が出て薄暗くなり始めた山を下った。
あれから50年以上も過ぎた2~3年前、親父さんの家を訪ねたときにあの時の話になり話が弾んだが、ふと漏らしたのは「生きて帰れないかと思った」と言う言葉だった。
吹雪と疲れの中で腹のすいた事はたとえようも無い。前を歩く背中の兎を見ては手を伸ばしてむしりとり、生で食べようと思った程なのでお分かり頂けるだろう。
下る途中ずっと河原角の人家の灯が見えた。人の灯りの有難さが身に浸みるようだった。その灯を目指して下り、やっと道に出た時の安心感はまるで「極楽浄土」に辿りついたかの様だった。
河原角の集落で川向こうに渡り、冬の間だけ人が通る山道を歩いて帰って来た。河原角で軒下にぶら下がった「固餅」を無断で頂いて食べようとも思ったが、やっとの思いで留まった。
わずかなデコボコに足を取られ、転び転びしながら、やっと親父さんの家に辿り着いたのは夜の9時頃だったと思う。
もしもバンドリを撃つつもりで二食分のお握りを持ってゆかなかったらどうなっていたか。恐らく空腹でみんなが動けず山を越すことは出来なかっただろう。
しかし、行く度に無事に帰った覚えはない。大体こんな思いをしていた。